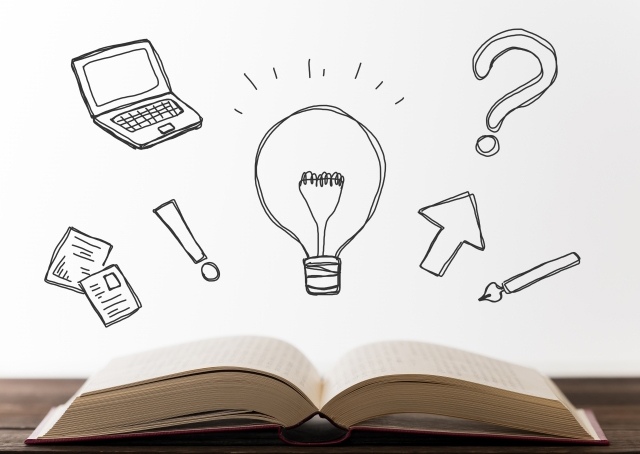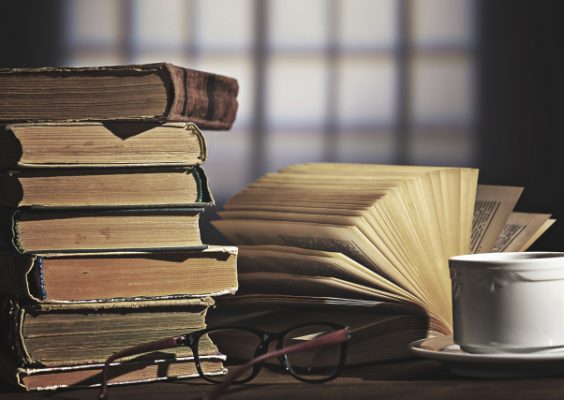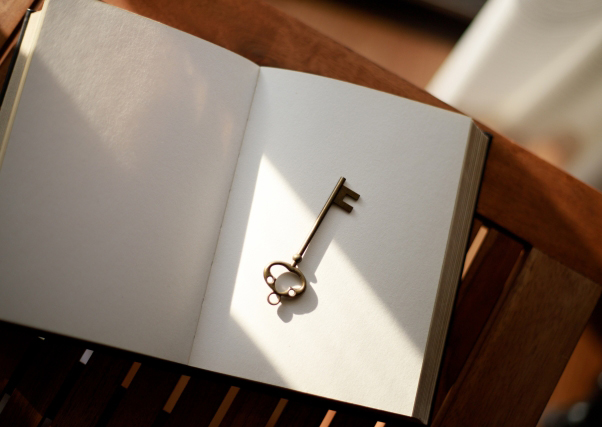直感で答えてください。どちらを選択しますか?
A:アマゾンのギフト券が1000円分もらえる。
B:600円払うとアマゾンのギフト券が2000円分もらえる。
実験をするとAを選ぶ人が結構多いそうです。もちろんギフト券ですから、現金より価値が低いとはいえ、Bのほうが400円得するのにもかかわらずAを選ぶんですね。もうひとつの実験を見てみましょう。お店で、あるテーブルに2つのチョコレートを山にして販売します。ひとつは、高級な有名ブランドのトリュフチョコレートで一粒16セント、もうひとつはメーカーの名前がよく知られているポピュラーなキスチョコで、一粒2セントです。お客がどちらか一方しか買えないよう「一人ひとつまで」と張り紙がしてあります。結果は、73%の客が高級チョコを選び、23%がキスチョコを選びました。次に、両方の値段を共に1セント値下げしました。選択の割合には変化がありませんでした。さて、さらに各々1セント値下げしたのです。そう、高級チョコは14セント、キスチョコはゼロセントです。ご想像のとおり、変化は劇的でした。69%の客がキスチョコを手にしたのです。私も同じ行動をとるでしょう。しかし、両社の差はいずれも14セントです。数式を使って恐縮ですが、高級チョコを食べる満足度をAとし、キスチョコの満足度をBとします。また、お金を払うことは不満足ですから、簡単にマイナスの満足度イコール支払い金額とします。すると
(A-16)>(B-2)と思う人が73%いる。
(A-15)>(B-1)と思う人が73%いる。
(A-14)>(B)と思う人が31%いる(になってしまう)。
ということになります。別にチョコレートの味が変わったわけではないので、A-Bの値は同じはずです。しかし、人がそれと引き換えに払うコストが、ゼロとそうでないときの差があまりにも大きいのでしょう。ゼロ(タダ)はそれほど私たちを魅了するんでしょうか?
ここから先は私の思考実験なんですが、もし、チョコレート実験をさらに続けて、今度は高級チョコの値段を順に下げていき、5セントになったとき(キスチョコは引き続きゼロ)に、高級チョコを買う人が再び73%になったとします。この場合、キスチョコが1セントからゼロセントになるときの価値が、高級チョコが15セントから5セントになるときの価値に等しいということになります。キスチョコが1セント以上の場合には、各々1セントずつ値下げしても、売れる比率は同じだったので、両方とも1セントの価値は同じだったのにです。ゼロコストの価値はとても大きいわけですね。最初に紹介した、アマゾンのギフト券も、600円払ったほうが通算では400円も大きい利益を得られるにもかかわらず、損失がゼロの方を選択する人は、600円の損失(コスト)と損失ゼロとの差が、1000円のリターン(2000円のリターン-1000円のリターン)よりも大きいということになりますね。
コストだけでなく、人はゼロを特別扱いしているようです。プロスペクト理論という学問によると、人はごく小さい確率でも、ゼロと比べると非常に大きく感じてしまうとされています。例えば、
(100万分の50万の確率)-(100万分の49万9千999の確率)と、
(100万分の1の確率)-(確率ゼロ)を比べると、
後者の方がはるかに大きく感じるわけです。1000万分の1の確率で2億円があたる宝くじの期待値は20円ですが、これを300円で買うと人にとっては、当選確率はその15倍以上に感じられるのでしょうか。
仕事をより効率的にするために進め方を変える、既存事業を縮小し新規事業に力を入れる、など新しいことに取り組もうとすると、何らかの抵抗が生じます。能率が悪いことがわかっていても、人は新しいことよりも慣れたことを好みます。このような保守傾向・現状維持傾向は、様々な要因が重なって起きていると思いまが、そのひとつに、「確実性がゼロではなくなる」ことに対する損失を大きく感じることがあるのではないでしょうか?確かに、これまでのやり方で引き続き仕事や経営をしていけば、これまでどおりの結果になると考えられます。しかし、ほんの少しでもやり方を変えることで、これまでと違った結果が出るかもしれないと思ってしまいます。たとえこの可能性がごくわずかだとしても、ゼロよりはずっと大きいと感じるため、ちょっとした変更にも抵抗感を持つのでしょうか。「ゼロ」の存在はそれほど大きいのでしょうね。
スーパーの駐車場が無料になるためにあと800円・・・。ネットショップの送料が無料になるのにあと1000円・・・。かく言う私も、「ゼロコスト」の魔力についつい引き込まれ、本来買わなかったはずのものを買っています。
(北原 康富)
参考文献:「予想どおりに不合理」ダン・アリエリー著 早川書房