PUBLICATION研究レポート
研究レポート
研究開発投資の事業性評価と意思決定
Part1.技術の事業性評価における不確実性のマネジメント
Part1. 技術の事業性評価における不確実性のマネジメント
技術を活用する事業化計画を立案する段階(技術の事業化)の意思決定プロセスにおいては、経営目標に対する貢献度、すなわち事業性を評価することが重要である。事業性の評価は、技術経営(MOT)に対する関心の高まりなどから、近年ますます重視されつつある。しかしながら、技術的なリスクや市場のリスクなどの不確実性が高い事業化計画に対して、その事業性を評価する手法については、まだ手探りの段階にある企業が多いようである。本稿では、不確実性のマネジメント手法を導入することによって事業化計画が内包する不確実性を定量化し、情報の理解と共有度を高め、意思決定の質の向上をもたらす手法を紹介する。
-
1.技術の事業化における事業性評価の一般的課題
日本インテグラートでは、企業の研究開発や新製品・新規事業の立案及び事業性評価の支援を行っている。主な内容は、事業化計画の経済的な価値の算出(バリュエーション)を行い、計画の実行に関する意思決定を支援することと、立案から意思決定に至る一連の業務プロセスとルールの構築を支援することである。このような支援業務において、各企業の様々な課題の解決に取り組んできたが、業種や企業の違いにかかわらず、事業性の評価に関する課題はある程度一般化できることがわかってきた。具体的には、以下の点を事業性の評価に関する一般的な課題として挙げることができる。
- a. 予測が困難なデータであっても、無理に「一点読み」を行って計算の根拠としている
- b. ゴールに大きな影響を与える不確実要因の理解があいまいで、優先順位(重要度)が整理されていない
- c. 技術に関する分析は詳細だが、市場や競合に関する分析が不足しているため、事業環境が変化した場合の対応が考慮されていない、一本のシナリオになっている
- d. 取りうるシナリオの全体像が示されないまま、稟議が通りそうなシナリオのみが検討されている
- e. 計算結果だけが示されており、計算過程がブラックボックスであるかのように思われ、信頼度を損ねている
- f. 計画の立案・評価が属人的なノウハウに依存しており、組織の経験・知識が生かせない、また、ノウハウが組織に蓄積されない
- g. 評価指標・プロセスの標準化が徹底しておらず、計画間の比較が難しい
-
2.不確実性のマネジメント手法
不確実性に対処するためには、将来にわたって数値と行動が変化することを前提とした手法が必要である。さらに、情報の共有を進める、という観点を加えると、不確実性のマネジメント手法のポイントは以下の3点に整理することができる。
- 1. 「幅」でとらえる
- 2. 取り得るシナリオを洗い出す
- 3. 情報を共有する
-
1. 「幅」でとらえる
予測どおりにならないことが当然ともいえるような不確実性が存在する場合、将来の製品価格やユーザー数、あるいは今後発生するコストなどの数値を「一点読み」することは、現実的とはいえない。むしろ、「一点読み」を行うことによって、企画担当者の恣意性を反映してしまうこともある。
このような課題に対処するためには、「幅」で考える手法を導入する必要がある。起こりうる変化を「幅」で認識することによって、不確実性を理解し、対応を検討することが可能となる。また、「幅」を持つ数値を定量分析することによって、ゴールに重要な影響を与える不確実要因を見出し、その優先順位を確認し、更には事業リスク(ゴールの振れ幅)を分析することが可能となる。その結果、技術や市場の不確実性がもたらす事業リスクには、いわゆる損失発生のリスクだけではなく、利益発生のチャンスもあることが理解され、守りだけではなく、攻めの計画立案のヒントが得られるようになる。 -
2. 取り得るシナリオを洗い出す
取り得るシナリオが一本しかないプロジェクトは珍しい。技術開発の成功・失敗はもとより、市場の選択・調達・生産・販売戦略など、複数のシナリオが存在するはずである。しかも、事業環境の変化によって、従来は考えられなかったシナリオが新たに存在する可能性もある。このような場合には、取りうるシナリオの選択肢を整理し、全体像を理解したうえで意思決定することが必要である。
全体像を理解しないまま、前例を参考にシナリオを一本に絞り込んでしまうと、不確実性がもたらす事業機会を逃してしまう恐れがある。また、シナリオが一本しか検討されていなければ、計画の実行段階で事業環境が変化した場合に、現行計画に固執してしまう原因ともなる。また、最終的に選択されたシナリオがベストであることを示すためにも、全体像に基づいて他の選択肢を検討しておくことが不可欠である。 -
3. 情報を共有する
不確実性に関する情報を共有するための工夫には、「定量化」「標準化」「視覚化」の3つのポイントがある。「定量化」は「どの程度不確実なのか」を数値化することによって、客観的な分析・議論と戦略の立案を容易にする。「標準化」は「他の計画とどちらが望ましいのか」比較すること、及び、異なる案件を迅速に検討することを可能にする。また、視覚化は「最小限の知識で素早く理解できる」ことを目指している。
この中で、なかなか取り組みがなされていないのは、「標準化」のようである。複数の事業化計画の中から優先順位を定めるために、全社的に明確な基準を設けて判断することは容易ではないが、社外・社内双方に対する透明性を確保するためにも「標準化」への取り組みを進めていく必要がある。
-
3. 事業性評価プロセスの例
以上で述べた不確実性のマネジメント手法を実践するプロセスの例を図1.に紹介する。以下、このプロセスに沿って手法を解説する。
図1 : 事業性評価プロセス
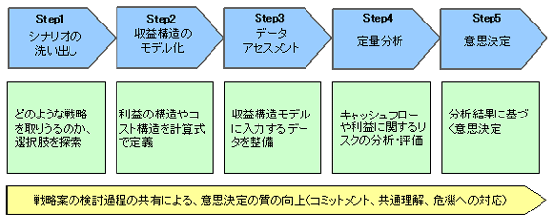
-
3-1. デシジョンツリーの活用によるシナリオの洗い出し
事業性を評価する場合、そのテーマの技術的な不確実性(テクニカルリスク)や市場における不確実性(マーケットリスク)の分析が必要である。このような分析を行っていくと、多くの場合複数のシナリオが想定される。そのような複数のシナリオを整理するために、デシジョンツリーを活用する。
図2 : 技術の事業家計画のデシジョンツリー例
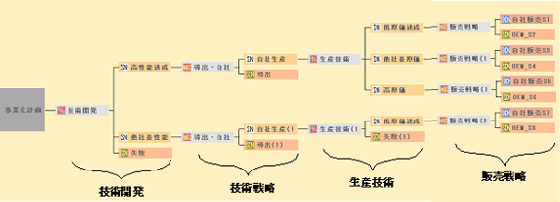
デシジョンツリーを作成して、その各々のシナリオの実現可能性を検討していくと、あるシナリオは一定の条件下では中止すべきである、という判断がなされる場合がある。例えば、他社もほぼ同じ時期に同等の機能を持つ新製品を投入してくるおそれがあるとする。性能と原価で他社を凌駕できない場合、その製品を発売して利益を上げることは難しいかもしれないが、計画段階ではまだ発売時期における性能も原価も読みきれない。この場合、性能と原価を再検証するタイミングを、開発開始から例えば1年後ということにあらかじめ定めておく。例えば、もしも性能・原価が他社製品に劣っており、採算が見込めない場合には販売を見合わせる決断をする、という検討が一年後に行われることをあらかじめ決めておくのである。プロジェクトの開始時点で計画を固定せずに、このように意思決定のタイミングを先送りして事業価値を高める(不採算計画を中断したり、より採算性の高いシナリオに変更する)ことは、リアルオプションの発想である。デシジョンツリーを活用することによって、比較的わかりやすくリアルオプションの手法を取り入れることができる。
-
3-2. 収益構造のモデル化
次のステップは、各シナリオに対応した収益構造の定義、すなわちモデル化である。収益構造の定義を行う際には、キャッシュイン構造の具体化と、キャッシュアウト構造の具体化があるが、一般的に難易度が高いのは、キャッシュイン構造の設計である。新技術の事業化や新製品を出す場合には、顧客のイメージが明確になっていないなどの理由から、キャッシュイン構造を考えるのが難しいことがある。このような問題に対処する一つの方法として、利益構造図を活用する手法がある。利益構造図は、下記の図3のように、利益やキャッシュフローの計算式をツリー構造で表現するものである。下記図の左から右のように、単純な構造の利益構造図から、末端の要素をブレークダウンしていくことによって、複雑な構造へ思考を展開させていくのである。
このように、収益構造をツリー構造で視覚化すると、自分の思考を展開させることに役立つだけでなく、収益構造モデルがブラックボックス化することを避けることができる。また、思考過程を視覚化できるため、個人のアイデアだけで無く、組織の経験・知恵を反映させていくことが可能になる。利益構造図は思考を支援するだけでなく、組織の暗黙知を形式知化していくプラットフォームとしても役立つのである。図3 : 利益構造図とその展開
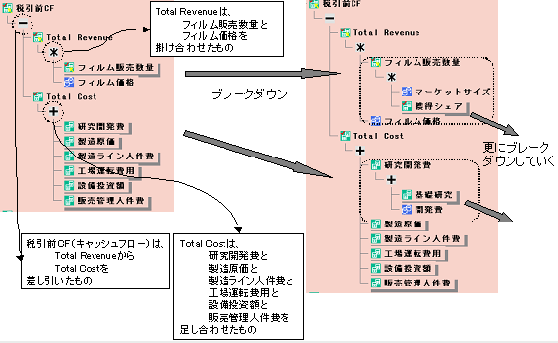
-
3-3.データアセスメント
収益構造モデルを作成すると、次に収益構造モデルの計算に必要なデータの収集と設定を行う。ここでは、不確実性を持つデータ(不確実要因)を「幅」で考えることが中心となる。例えば、今後5年間の市場の伸びを予測する際に、5.0%というように一点読みをしてしまうのは現実的ではないと考え、5.0%を基準値とし、3.5(最小値)~6.5(最大値)%というように幅で設定を行う。この手法を用いると、数値の不確実性を計画に反映させることが出来る。つまり、計画時点で数値の精度が低いものは幅が広くなるし、精度が高いものは幅が狭くなる。
ここで重要なことは、幅の設定ルールを定めておくことである。幅の設定方法を標準化せずに、まちまちの運用を行ってしまうと、案件間の比較ができなくなってしまう。企業や部署によって、データの精度を考慮した上で、10回に1回発生すると考えられる値を最大・最小値に設定するルールや、1000回に約1回のレベル(統計的には3σ)で最大値・最小値に設定するルールを採用している。
また、不確実性を計画に反映させる場合には、自社でコントロールできない外的なものと、自社で戦略的に決定できる内的なものの2種類に分けて考えるとよい。例えば、市場価格や為替レートなどは自社でコントロールができないが、広告宣伝費などは自社で戦略的に決定ができる。このような不確実性の違いを整理しておくことによって、計画案の検討が効率的に進められるようになる
更に、このような不確実性は、定量分析を行う際に用いる発生確率分布としてとらえることができる。データ毎にどの確率分布タイプをあてはめるかは、過去のデータを分析して客観的に推定することが望ましいが、新技術の事業化に際してはデータが不足することが多いため、自社でコントロールできない数値の発生確率は、自然界によく見られるように正規分布に従う、または三角分布に従うと考え、自社で任意にコントロールできる数値の発生確率は、一様分布に従うと考える簡便法がある。自社でコントロールできるが、およその基準値があり、最小・最大の幅があるものは、正規分布または三角分布に従うと考えても良いだろう。ここで設定する分布は、後述する確率分布分析に利用されるパラメーターである。図4 : 確率分布タイプの例
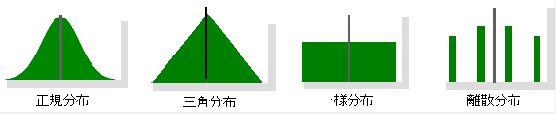
-
3-4. 定量分析の手法
収益構造をモデル化し、データを設定すると、売上や利益などの様々なゴールを算出することができる。事業性の評価に用いる指標は企業によって異なるが、企業価値の最大化を経営目標として掲げている場合や、計画が長期間にわたる場合には、評価指標に資本コストと時間の観念を反映させるため、NPV(割引キャッシュフローの現在価値)を採用している例が多い。NPVの代表的な算出手法としては、事業の不確実性に応じ、不確実性の低い方から、DCF、シナリオ別DCF、モンテカルロDCF、デシジョンツリーアナリシスなどを用いる。また、事業性評価を効率的に支援する分析手法として、What-If分析、感度分析、確率分布分析(モンテカルロシミュレーション)などがある。
図5 : What-If分析
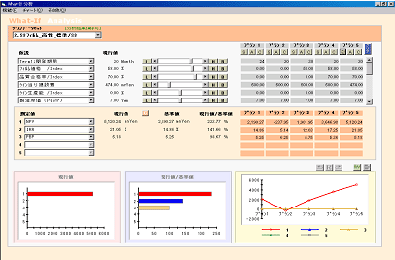
What-If分析
What-If分析は、不確実要因がもしこういう条件ならゴールはどうなるか、ということを示す分析である。事業化計画の立案・検討過程では、複数の不確実要因が様々な値をとる場合のシミュレーションが行われるが、What-If分析機能を備えたソフトウエアを活用すると、複数の値を変化させる試行錯誤の効率が大幅に上昇する。議論の場においても、その場で条件を変更した場合のゴールを共有することができるため、意思決定の支援にも強力な効果を発揮する分析手法である。図6 : トルネードチャート(左)、折れ線グラフ(右)
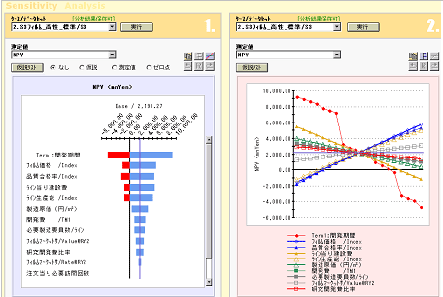
感度分析
感度分析は、ある不確実要因が最小値から最大値まで変化する際に、ゴールがどの程度変化するのか、影響度を示す分析である。その際、他の不確実要因は基準値のまま変化させない。横軸でゴールの変動幅を示し、影響度の高い不確実要因を上方に、低い要因を下方に整理したものがトルネードチャートで、すべての不確実要因に共通の横軸を設定し、縦軸にゴールの変動を示したものが折れ線グラフである。図7 : 確率分布チャート(左)、バーチャート(右)
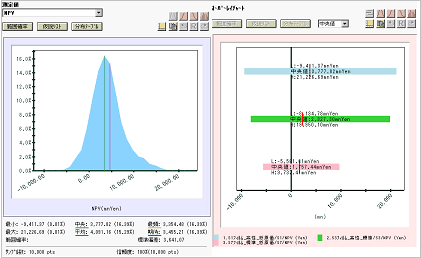
確率分布分析(モンテカルロシミュレーション)
データアセスメントにおいて、不確実要因の変動幅だけでなく、正規分布・三角分布や一様分布といった発生確率分布を検討しておくと、確率分布分析が可能となる。確率分布分析は、複数の不確実要因が発生確率分布に従って変動する収益構造モデルを、コンピューターに数百回~数千回以上計算させ、そのゴールの分布を示す分析である。目標を達成する確率や、最頻値・最小値・最大値を知ることができる。横軸を各回の計算結果とし、縦軸を発生確率として分布を示す確率分布チャートや、複数のシナリオの最頻値・最小値・最大値を比較するのに便利なバーチャートなどがある。 -
3-5. 意思決定
以上のプロセスを経て、デシジョンツリーに立ち戻り、起こりうるシナリオの全体像を確認して意思決定を行う。
図8に示されているように、デシジョンツリーの分岐点には、発生確率(成功確率)を定義する場合と、有利なシナリオを選択する(例:設備投資額が最も小さくなるシナリオを選択する、売上が最大になるシナリオを選択する)、などの意思決定ルールを設定する場合がある。図8 : デシジョンツリーを活用した最適案の選択
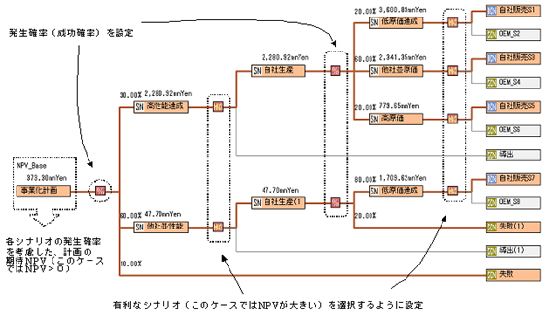
図8は、洗い出した各シナリオについてNPVを計算し、各シナリオの発生確率を掛け合わせ、また技術戦略・販売戦略上有利なシナリオを選択するケースである。このケースでは、技術導出・OEM販売とも将来の交渉によって条件が変動するため、計画立案時には自社生産・自社販売のシナリオのみを検討し、事業化の意思決定を行おうとしている。各シナリオの発生確率を考慮した、この計画の期待NPVは正の値になっており、NPVが正の場合には計画を実行するというルールを定めている場合には、この計画にゴーサインが出されることになる。
デシジョンツリーの分岐点に設定する成功確率の推定は、過去のデータを可能な限り活用する、学識者や目利きの意見を尊重する、などの方法はあるが、その性質上、正解が得られる保証は無い。この点を理解した上で、成功確率の議論を行う評価委員会を設け、その場での結論を会社としてオーソライズする(それ以上の議論を行わない)、という仕組みを構築することも一案である。 -
4. 事業リスクの低減プロセス
事業化計画の様々な不確実要因によって、ゴールにも幅、すなわち事業リスクが存在する。計画開始以降は、定期的に、または予め設定したマイルストンにおいて、各不確実要因が計画値とどの程度乖離しているかを分析し、事業リスクの低減活動を行うことが重要である。
計画の立案以降は、事業化の実行に伴って得られた情報や調査によって入手した情報を基に、計画時に立てていた不確実要因検証していく。不確実要因の検証によって、当初不確実性の高かった要因を次第に知識化し、不確実性の「幅」を低減して行く(「幅」が拡大することもある)。その結果、相対的に「幅」が大きくなった(不確実性の高くなった)要因に対しては新たな対策を検討する。この過程においても、計画の立案段階の分析手法を活用し、常に不確実要因の優先順位を把握して、適切なタイミングにリスク低減対策を行う。図9 : 事業リスクの時系列比較(確率分布バーチャート)
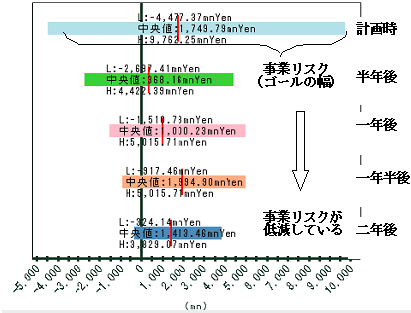
4. 事業リスクの低減プロセス
計画の立案以降は、事業化の実行に伴って得られた情報や調査によって入手した情報を基に、計画時に立てていた不確実要因検証していく。不確実要因の検証によって、当初不確実性の高かった要因を次第に知識化し、不確実性の「幅」を低減して行く(「幅」が拡大することもある)。その結果、相対的に「幅」が大きくなった(不確実性の高くなった)要因に対しては新たな対策を検討する。この過程においても、計画の立案段階の分析手法を活用し、常に不確実要因の優先順位を把握して、適切なタイミングにリスク低減対策を行う。 適切なタイミングにリスク低減対策を行うためには、マイルストン計画を立案することが有効である。マイルストン計画においては、あるフェーズが完了するタイミングや、半期毎など、あらかじめタイミングを定めて、どの不確実要因を検証するかを計画しておく。特に、デシジョンツリーで洗い出したシナリオの分岐点に相当するタイミングにおける検証は重要である。シナリオの分岐点で不確実性を検証することによって、事業環境の変化に対応した別のシナリオを適切なタイミングに選択することが可能となる。
上の図は、計画の進行に伴って、事業リスク(ゴールの幅)が低減している例である。 -
5. おわりに
本稿では、事業性の定量評価手法における不確実性のマネジメントに絞って紹介を行ったが、技術の事業化にあたって、定量評価手法のみに依存して適切な意思決定が行えるとは限らないことを付言しておきたい。定量評価と対になるものとして、定性評価、すなわち強みや弱み、特性などを数値以外で分析することが広く一般に行われている。SWOT分析や、4P分析などがその例である。しかしながら、定性評価には主観が強く反映されたり、表現が曖昧になってしまったり、という欠点がある。また、本稿で紹介している定量評価手法には、執念や興奮といった、ビジネスを支えるヒューマンな要素を表現しにくいという欠点がある。読者各位におかれては、このような定性評価と定量評価のバランスを勘案したうえで、不確実性のマネジメント手法を事業性評価にご活用いただければ幸いである。
このような課題が生じている背景には、企業を取り巻く事業環境の変化が今までになく速くなっていることがある。そのため、技術や市場などに関する不確実性が今までになく増大しているのである。上記の事業性の評価に関する一般的な課題のうち、a.~d.については、「不確実性に対処できていない」ことが主な要因となっている。また、e.~g.については、事業性の評価プロセスにおいて、「情報の共有」が出来ていないことが主な要因である。すなわち、上記の課題の解決のためには、不確実性に対処できるように事業性の評価手法を変革し、情報の共有を進めることが必要なのである。
■ 執筆者
宮本明美
日本アイビーエム、日本アーンスト・アンド・ヤング・コンサルティング(現日本キャップジェミニ)を経て現職。
ノースカロライナ大学キーナンフラグラービジネススクールMBA
小川 康
東京海上火災保険、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンを経て現職。
ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA
■ 掲載元
月刊テクノロジー・マネジメント
株式会社フュージョン アンド イノベーション
2004年6月号 P64-71 「技術の事業性評価における不確実性のマネジメント」

