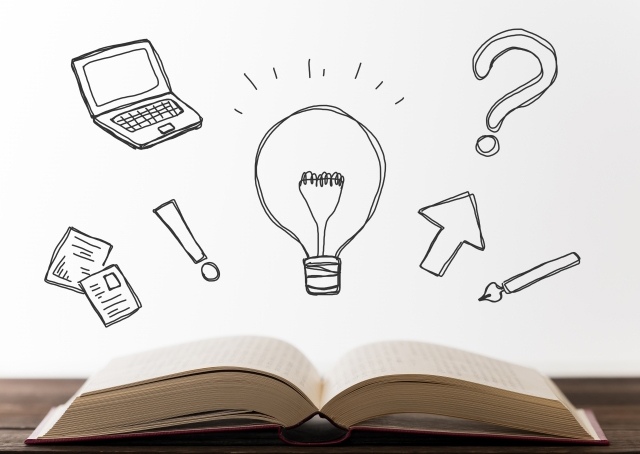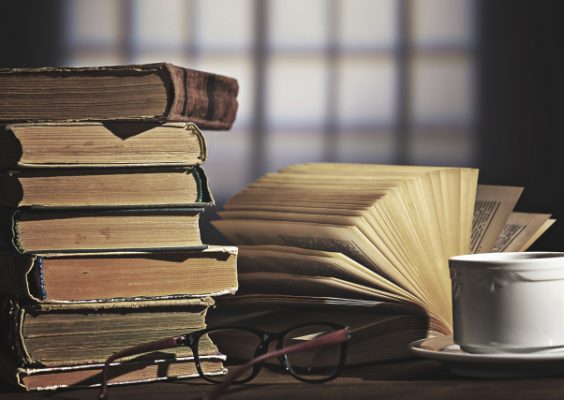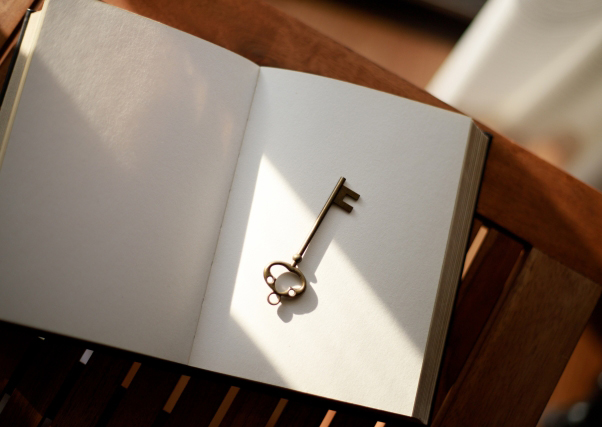まずはこちらの動画をご覧ください。(画像をクリックすると弊社のYouTubeチャンネルにアクセスし動画が再生されます)
この動画は、私のピアノ演奏を撮影したものです。もともと子どもの頃にピアノを習っており自宅に電子ピアノがあるのですが、大人になって久しく弾いていなかったところふと思い立って数年前からちょくちょく弾いていました。そして最近、自宅近くにグランドピアノが置いてある個室スタジオがあることが判明したので、好奇心から思い切って利用してみて、その場でたまたま思いついてこの動画を撮影しました。下手な演奏ですみません。
動画を後日自分で見返して思った第一印象は「うわ、音が硬いなぁ」というものでした。電子ピアノとグランドピアノという違いのせいかもしれませんが、自宅で電子ピアノを弾いていた時の感覚ではもっとスムーズな音の響きだったように感じていました。自分の感覚と実際に動画で聞こえてきた印象のギャップにショックを受け、「せっかく弾くのであれば、より柔らかく豊かな響きの音色にしたいな」と今後一層努力をしたいなと思った次第でした。
さて、ここまで考えたところで思い浮かびました。「ピアノ演奏を撮影したことに端を発する一連の思考の流れは、ピアノ演奏に限らず物事を改善する際に重要となるポイントとしても活用できるのではないか」と。そこで今回のコラムでは、私のピアノ演奏を撮影して気づいた、物事を改善するためのポイントを3つに分けて紹介いたします。肩肘張らず気楽に読んでいただければ幸いです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<ポイント①自分が作ったものを後から客観的に見直してみると、作った際の主観的な印象とはかなり異なる>
これまで自分がピアノを弾いている様子を動画で撮影したことはなく、普段自宅で電子ピアノを気ままに弾いている時は、それなりに奇麗な音色で弾けていると自分で思っていました。しかし今回たまたま動画を撮ったことで初めて自分の演奏を客観的に観る機会が生まれ、自分が普段思っていたイメージに比べて実際に動画で見聞きしたものが全く異なり、粗が目立っていることに気づきました。また音だけでなく(これまで意識したことがなかった)指や腕のラインや使い方も美しくない印象を持ちました。
このように、自分が物事の作成や遂行に関わった当事者だと、自分が作成遂行したものに対する評価は、内側から見た自分の主観による「こうありたい」という理想のイメージに知らず知らず近寄ってしまい甘くなるバイアスがかかるのかもしれません。従って、物事を正しく改善したいなら、いちど自分が作成遂行した状態から敢えて距離を取って眺める機会を持つことで、公平で客観的な外部の視点で様々な気づきが得られるかもしれません。例えば事業計画であれば、一通り計画をまとめた後で一晩置いて頭をリフレッシュしてから再度目を通してみると、作っていた時には見過ごしていた課題が見つかるかもしれません。忙しくて見直す時間がなかったり、自分の内部にある理想的なイメージが壊れることを恐れたり、などでなかなか後から見返してみるモチベーションは起きにくいものです。それでも、その後の改善の手がかりを得るために必要なプロセスだと言い聞かせて、時間を取ってグッと歯を食いしばって見返すことが、改善に向けた大きな第一歩につながります。
<ポイント②改善のためには、真の原因まで掘り下げる必要がある>
先に書いた通り、まず自分が動画を見て気になったのは音の硬さでした。そこで、柔らかいタッチで弾く技術を身に着けるべく、Web検索で調べてみたところ果たして様々な方法が出てきました。そもそもピアノが音を出す仕組みから解説して合理的なテクニックを説明しているサイト、子ども向けにわかりやすく手の形や感覚をコンパクトに紹介しているページ、ピアノの音色の種類と手法を網羅的に掲載しているリスト…また、最近は検索時にAIによる回答が載っており、ChatGPTのようなAIに質問して(AI曰く)『本質的なポイント』を教えてもらうことも可能です(といってもポイントを絞ったというよりは大分広範にわたる記述となっていますが)。ただ、ここまで多くの検索結果が一気に出てくると「では、結局どうすれば良いのか?」と迷ってしまいます。どの方法が自分に適しているのか判断がつきませんし、かと言ってすべての結果に目を通して一通り試してみて自分にあうやり方を探るほどの時間はありません。何から手を付けてよいかわからず、途方に暮れてしまいました。
つまるところ、発生している問題点に対して直接的な対処方法は数多く存在するものの、それら対処方法の有効性を検討して取捨選択・導入することは容易でなく、また実施したとしても根本的な問題解決につながっている確証は得られません。物事の改善のためには、問題点が発生する真の原因まで掘り下げたうえで整理して対策を検討する必要がありそうです。その具体的な方法については、過去のインテグラートインサイト・コラム「失敗から成功へ:『振り返りマップ』のすすめ」(https://www.integratto.co.jp/column/208/)が参考になるかもしれません。
<ポイント③困ったら専門家に頼ろう>
ポイント②で書いたように困ってしまった結果、現在の結論としては「自分であれこれ悩むよりは、いちどピアノの先生に見てもらおう」と思い至りました。直接的には音の硬さを何とかしたいと思いましたが、他にも指の運びがぎこちなかったり音の強弱がまばらだったり、など様々な問題点もありそうなので、総合的に見てもらったうえで弾く時の姿勢や意識する点・練習方法など教えを受けたいと考えています。
「餅は餅屋」という諺がありますが、物事の改善を行うにも当事者個人では知識経験に限界があります。ポイント②で書いた真の原因の掘り下げや適切な対処方法を実施するためにも、まずはその道の専門家に診断とアドバイスを受けることをお勧めします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上、最近個人的に経験したことから弊社の事業領域につながるかなと思ってフランクに書いてみましたがいかがでしたでしょうか。動画での私の拙い演奏を見て「ここはこうした方が良い」などアドバイスいただける読者の方がいれば大歓迎ですので是非遠慮なくご連絡ください!また、事業計画立案や投資評価などでお困りの方がいらっしゃれば、専門家の弊社が支援いたしますので是非お気軽にご相談ください!
(楠井 悠平)