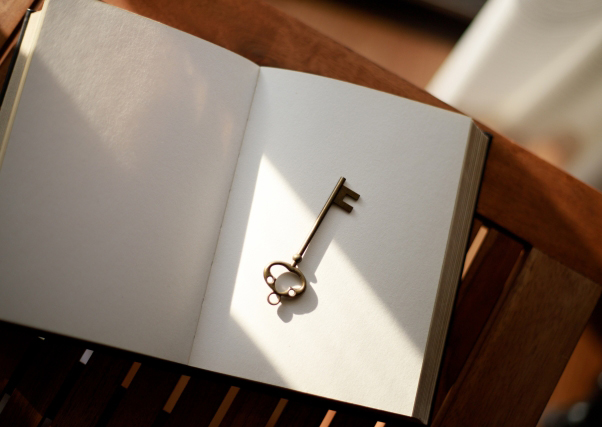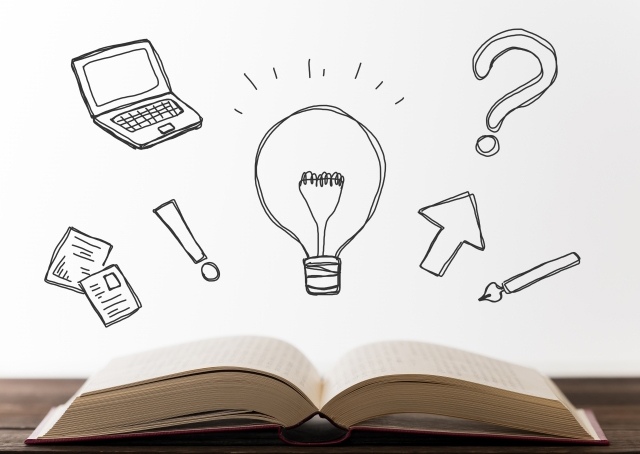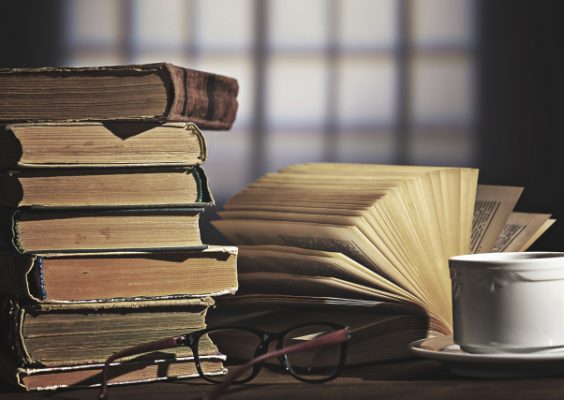弊社では、製品開発・設備投資やM&A等の事業投資の意思決定を支援しています。例えば、あるプロジェクトに2013年までに10億円投資すると、2018年までに投資回収できる確からしさは70%程度、というようなシミュレーションを行い、投資の実行可否に関する意思決定の材料として提供しています。
このシミュレーションの結果、ある投資を実行する意思決定が下されたとします。弊社の観察によりますと、この意思決定の結果が、利益目標として明示されるどうかは、業種・企業によって大きく異なります。つまり、2018年までに投資回収するということが目指すべき目標として示される場合もあれば、利益目標については振り返りされずにあいまいに放置されてしまう場合もあります。読者の皆さんは、せっかく議論した利益目標をあいまいにしてしまってはダメじゃないか、と思われるかもしれません。しかしながら、利益目標が明確に設定されず、意思決定の際に議論された採算性についてはあいまいなまま放置される、ということが意外に多いのです。
意思決定と利益目標設定が一致している例は、総合商社に多く見られます。総合商社では、意思決定されると、原則として利益目標必達です。利益管理も厳しく、赤字が3年続くとその事業から撤退する、というような撤退基準が大手を中心に採用されています。
意思決定の際に議論された利益目標があいまいなまま放置されている例は、製薬会社、総合化学、大手自動車部品、精密機器など、かなり幅広く見られます。もしかすると読者の皆さんの会社でもあることかもしれません。
このような利益目標の位置づけに違いが見られるにもかかわらず、事業投資の意思決定プロセスは、業種を問わず類似しています。例えば、予想される投資と利益を見積り、採算がとれると判断されれば、実行する意思決定が下されます。そして、意思決定の後は、担当部門がとにかく頑張る、ということも、ほとんどの会社で実行されます。このようにプロセスが類似しているにもかかわらず、利益が必達目標となる場合と、あいまいなままになる場合が出てくるのは大変興味深く感じられました。
この違いは、何が原因なのか。筆者は、投資という行動に関する意思決定なのか、利益に関する意思決定なのか、という目的の違いによるのではないかと考えます。
実際に、意思決定時に議論された利益目標があいまいになっている場合に関係者と会話してみますと、予測が外れやすいこと、意思決定者と実行者が異なるため管理が行き届かないこと、投資対象の利益が部門収益の中に埋もれてしまい把握できないこと、などが説明されます。しかし、総合商社の一部では、何年先の利益でも必達目標としていることを考えると、これらの説明は言い訳にしか聞こえません。そこで、もう少し聞いてみますと、製品開発や工場立ち上げ・買収交渉などの投資行動に全力を尽くしていて、利益など投資行動の先のことまで気が回っていない状況が見えてきました。実際、そのような会社では、投資額には緻密な管理が行われる傾向が見られます。一方で、利益を投資(過去の支出)と結び付けて振り返る仕組みを持つ会社はまだ少ないようです。
投資面、つまり製品開発等を重視する企業にも、あいまいなまま利益目標が振り返りされない状況に問題を提起する人はたくさんいます。それでもなお振り返りをされない現実には、「わたし・つくる人、あなた・売る人」のような機能別組織の弊害が垣間見えます。
機能別組織の典型例は、研究・開発・製造・販売に部門が分けられている状況です。これらの部門をつないでいるのは、時間軸です。研究から開発へ、開発からやがて製造・販売へと時間の流れで組織はつながっています。ですから、組織としても、研究・開発の投資と、製造・販売の利益が、時間差を持ってつながることが自然です。機能別組織を隔てているのは、単に機能差だけではなく、時間差でもあることに注意すれば、互いにつながりやすくなるのではないでしょうか。
具体的には、研究・開発で行われた投資がもたらす5年先の利益目標は、1年後には4年後の目標になり、やがて5年後には製造・販売部門の利益目標になります。研究・開発部門の投資が、時間の経過とともに製造・営業部門の利益目標に円滑に推移していくように、少なくとも年に1回は、意思決定の材料であった投資と利益の振り返りを行うべきです。時間差はあっても、常に投資と利益がつながっている仕組みが必要です。
多くの企業が投資を削減しようとしている現在、直近の投資の削減によっていつ頃、どの程度の利益が失われるのか、投資と時間差のある利益のつながりを振り返ったうえで削減することが必要ではないでしょうか。この確認を、研究・開発部門だけに任せてしまうと、部分最適に陥るおそれがあります。影響は、数年後以降の販売部門、ひいては会社全体の利益にあらわれるでしょう。このような部分最適による損失を避けるためには、投資に関する意思決定と、時間差のある利益を適切に結びつける、機能別組織の相互連携が必要です。研究・開発部門と、製造・営業部門が連携しなければ、全体最適にならないわけです。この部門連携は、個別の投資に対する利益が議論される段階から実行されると良いでしょう。
投資と利益に関して、機能別組織が連携している状態は、投資の意思決定と利益目標設定が近づいている状態です。皆さんの会社では、投資の意思決定と、利益目標設定はどこまで近づいていますでしょうか。それは、部門間の連携状況を見ればわかるはずです。
投資が適切に利益を上げなければ、次代の投資余力が細ることは自明です。心地よい部分最適をあきらめ、連携を密にした全体最適を目指すことが必要でしょう。
(小川 康)