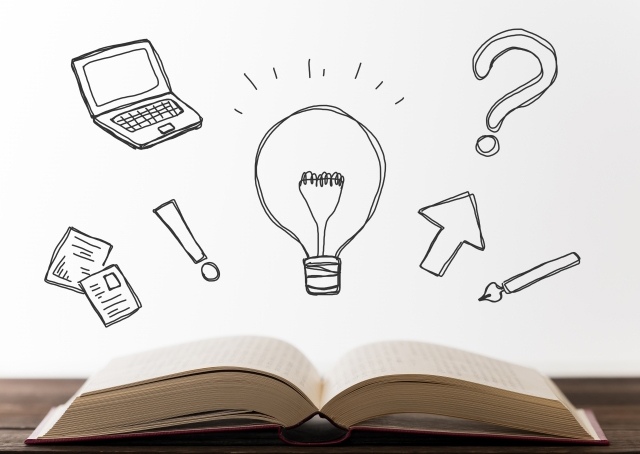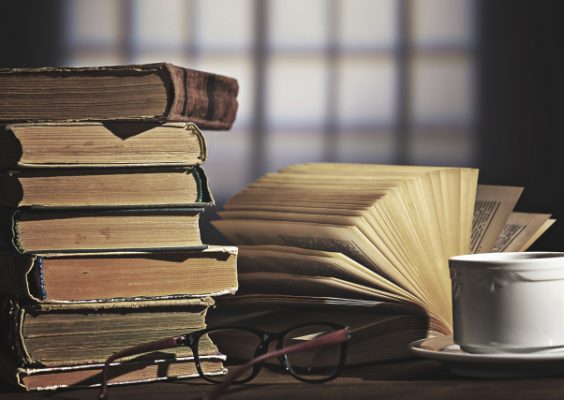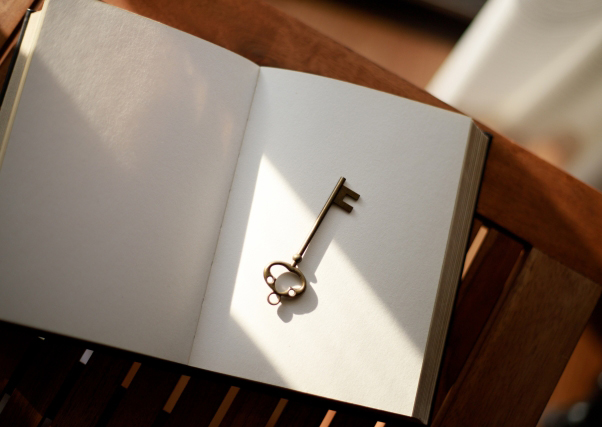筆者がビジネススクールに入ってから最初の授業が管理会計の授業でした。
テアダウンとは何かを理解する一環で、当時まだまだ利用されていた「使い切りカメラ(レンズ付きフィルム)」をメーカー別に分解し、比較分析し、報告する授業を行っていたことが印象に残ります。
原価計算やバランススコアカードなども授業で取り上げられましたが、予算計画やチェンジプロセスマネジメントなど、インテグラートが手掛けている事業性評価や事業ポートフォリオ評価につながる内容のものもあったので、より強く記憶に残っています。
私たちインテグラートは日常的に会計の知識と会計情報を使って事業性評価や事業ポートフォリオ評価を行っています。したがって、財務会計とは近しいと感じますが、同じ会計の名前を冠する管理会計とはどのようなつながりがあるのでしょうか。また、そもそも財務会計と管理会計の違いは何かという点も含め、今回のコラムで考察したいと思います。
管理会計とは何か
「管理会計 第5版」では、「管理会計(management accounting)とは、経営戦略を策定し、経営上の意思決定とマネジメント・コントロール(期間計画と計画に基づく活動のモニタリング)を通じて経営者を支援する会計である。」と定義されています。また、管理会計と財務会計の違いについて、「財務会計は投資家による投資意思決定、管理会計では経営者による意思決定が主要なテーマになる」としています。財務会計は情報の利用者が外部のステークホルダーであり、財務諸表を通じて主にその会社への投資判断に使われるのに対し、管理会計は経営者が予算報告書や中長期の計画書などを通じて戦略策定や経営意思決定に使われるという違いであると言えます。加えて、財務会計で扱われる情報は、企業会計原則や会社法、金融商品取引法、法人税法などによって内容が規制されますが、管理会計上の情報にはそのような法規制はないというのも大きな違いです。
それでは、管理会計がカバーする領域、守備範囲はどのようなものでしょうか。
大きく分けると以下の2つが挙げられます。
(1)過去から現在の業績管理
過去の原価などの実績から今後の目標となるべき原価などを設定し、管理していく領域です。主なトピックとしては原価管理、利益管理などが挙げられます。管理会計はもともと、19世紀のアメリカでの繊維産業や鉄鋼産業などにおける産業革新において、生産技術の手法として標準原価計算が生まれたことがルーツとなっています。目標となる標準原価に対する実際の原価との差異分析から、製品開発段階から始まる、将来の原価低減活動である原価企画(Target Costing)のように次項の経営戦略・経営意思決定につながる考え方も発展してきました。
(2)現在から未来の経営戦略と経営意思決定
前述の通り管理会計は経営者を支援する会計であることから、もう1つの領域として経営意思決定へ管理会計を役立てるというテーマがあります。この領域では、過去の実績情報は将来の予測の基礎にはなりますが、それだけでは意思決定に役立ちません。そこで、見積や予測が情報として必要になります。前掲書では、1)未来情報が必要、2)正確性より意思決定の目的に適合したデータが必要、3)定量的データと定性的データの両方が必要と指摘しています。私たちが事業性評価で接する現在価値法(NPV)、内部利益率法(IRR)やデシジョンツリー法等に加え、線形計画法なども経営意思決定の手法に含まれます。
また、事業投資のプロジェクト意思決定に関連して、管理会計では「プロジェクトコントロール」として進捗度統制と事後監査の2点を挙げています。進捗度統制は計画の進捗状況を測定することですが、プロジェクトコントロールの焦点はむしろ事後監査にあるとしています。これは、プロジェクトの計画段階の評価と計画後の評価の整合性を取り、計画実施以降のコントロールと監査をしっかり行うことで効率性重視の経営につなげるという趣旨です。これは私たちが依拠する理論であるDDP(仮説思考計画法)の中のマイルストンプランニングに極めて近い考え方ですが、この領域も管理会計の一部となっていることが分かります。
管理会計の範囲と組織
上述の通り、管理会計の経営意思決定を支援する役割の部分は、私たちが扱っているプロジェクトの事業性評価やポートフォリオ評価による経営意思決定と同じものであることが分かります。しかし、私たちが接するお客様の中でも、管理会計という言葉や、その名前がついた部門の方に出会うことが少なく感じられます。つまり、組織の中で「管理会計」の名前で機能や役割の範囲を定義しづらい、分かりにくい領域とも言えるではないでしょうか。管理会計の守備範囲が幅広いゆえに、部門によって管理会計とは何かという定義が異なることが起こりうる(製造部門なら原価管理のことであり、経営企画部門であればバランススコアカードのことである、といったように)のかもしれません。しかし、管理会計そのものをカバーする部門はなくても、管理会計的な考え方、すなわち、セグメント化された組織単位における、過去から未来にわたる業績を適切に測定・分析することを通じて経営を可視化し、経営者の意思決定を支援することは色々な部門でこれからもますます必要とされるでしょう。
ところで、私たちの会社は「ビジネスシミュレーションの提供を通じて、新たな製品やサービスの創出に貢献する」を企業理念に掲げています。私どもがシミュレーションの対象として扱っているのは未来の会計情報であり、私たちが提供しているサービスは、新たな製品やサービスの未来の会計情報を予測し、シミュレーションによって変動させて隠れたリスクを可視化し、価値を予測することで経営意思決定を支援する行為と言えます。その点でまさに管理会計の領域に含まれる活動であると定義できます。
今後、IFRSが導入されると、事業投資の評価手法も従来の日本企業で多くみられた投資回収期間法(PBP)から現在価値法などのDCF法が増加すると見られています。
私たちのお客様はこれまで、研究開発に関わる方々が多くおられました。今後はそれに加え、CFOの方々とのつながりを持つため、昨年日本CFO協会の会員となり、セミナーも開催しております。引き続き経理部、財務部といった会計に関わる方々にもつながりを深めるべく、努力したいと思います。
(井上 淳)
(参考文献)
櫻井通勝「管理会計 第5版」、同文舘出版、2012年
浅田孝幸・頼誠・鈴木研一・中川優「管理会計・入門」有斐閣アルマ、1998年